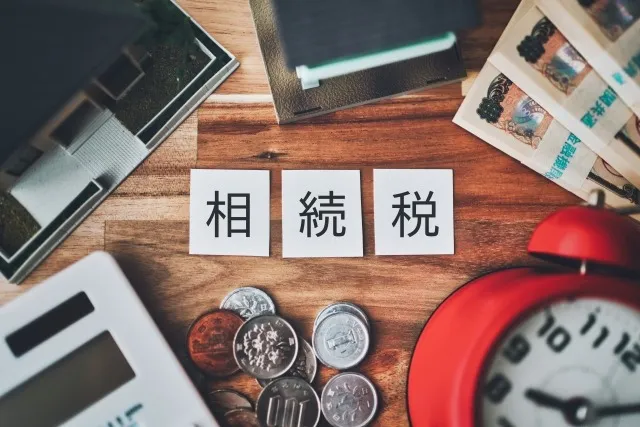意外と知らない年次有給休暇の落とし穴について社労士が解説!③〜年次有給休暇の計画的付与・時期指定の義務〜
2025/04/07
はじめに
近年、コロナ禍で加速した働き方改革をはじめ、人手不足による労働環境の見直しの観点から、休暇に関する企業の考え方が変化しつつあります。その中でも年次有給休暇は労働基準法上規定された労働者の基本の権利です。
年次有給休暇は、一定の要件を満たす従業員に対して付与されるもので、労働基準法では、労働者の健康を守るために、休日のほか毎年一定日数与えることを規定していますが、当ブログでは今回から、年次有給休暇に関して、意外と知られていない論点や間違えやすい事項を複数回にわたって解説します。
第3回は年次有給休暇の計画的付与・時期指定の義務についてです。
年次有給休暇の計画的付与
労働基準法において、年次有給休暇の計画的付与に関しては次のような条文があります。
|
第三十九条 ⑥ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 |
年次有給休暇の計画的付与とは、年次有給休暇の取得率が低い状況を鑑み制定されたものであり、従業員が付与されている有給休暇のうち5日を超える部分について、使用者が時期を指定して与えることができるようになる制度です。例えば、年次有給休暇を20労働日有している労働者については、15労働日を計画的付与の対象とすることができます。
計画的付与をするためには、労働組合もしくは労働者を代表するものとの間で、計画的付与をする旨の労使協定を締結する必要があります。この労使協定については労働基準監督署への届出は不要です。
計画的付与を行うにあたっては、事業場全体の休業によって一斉付与する方法か、有給休暇の付与計画に基づいた個別付与による方法が一般的です。この計画的付与によって万が一、年次有給休暇の日数がない従業員についても同様の休業をさせた場合は、休業手当を支払う必要があるため注意しましょう。
年次有給休暇の時期指定の義務
労働基準法において、年次有給休暇の計画的付与に関しては次のような条文があります。
|
第三十九条 ⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。 ⑧ 前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。 |
前回解説した年次有給休暇の時間単位付与や、上記の年次有給休暇の計画的付与の規定により、一定程度有給休暇の取得率は改善したものの、いまだに50%台に留まっていることに鑑み、労働者が時期を指定していなくとも、有給休暇のうち年に5日は、使用者が労働者の意見を聞き、その意見を尊重して基準日から1年以内に取得時期を指定し取得させることが義務付けられました。
ただしこの規定は、繰り越される日数を除いた有給休暇の日数が10日以上ある労働者のみが対象であり、さらに、労働者自身で時期を指定して取得した分や、年次有給休暇の計画的付与によって取得させた分は、当該5日から差し引かれることとなります。例えば、年次有給休暇を20労働日有している労働者が自身で2日間有給休暇を取得した場合は、残り3日間については基準日から1年以内に、使用者が時期を指定して有給休暇を取得させなければならないこととなります(もしくは残り3日間についても、労働者が自身で取得しても構いません。)。
要は年に5日はどのような形であっても必ず有給休暇を消化しなければいけないということです。仮に使用者が時期指定の義務を果たさなかった場合は、消化できていない労働者1人につき30万円以下の罰金という罰金規定が適用されてしまいます。
基準日の考え方について
通常は入社から6ヶ月を経過した場合に初めて有給休暇が付与されますが、会社によっては入社時に即時付与させたり、入社時とは別の基準日に付与させることもあります。それぞれの付与のタイミングに応じた有給休暇の付与期間は下記のとおりです。

まとめ
いかがだったでしょうか。
原則として1年以内に5日については、年次有給休暇を付与しなければならないという義務規定は、平成31年4月1日から施工されており、もしかしたら今まで知らなかった経営者の方もいるかもしれません。年間5日も最低条件ですので、労働者のワークライフバランスの促進のためにも、経営者の方には有給休暇の取得しやすい職場の環境づくりを整備していただきたいと思います。
次回は年次有給休暇の賃金及び、年次有給休暇に関する代表的な裁判例について解説します。
磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務・労務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。
(※当該記事は投稿時点の法令等に基づいて掲載しております。当ウェブサイト上のコンテンツについて、できる限り正確に保つように努めていますが、掲載内容の正確性・完全性・信頼性・最新性を保証するものではございません。)
----------------------------------------------------------------------
株式会社磯会計センター
〒308-0844
茨城県筑西市下野殿852-3 メゾンルーチェⅡ
電話番号 : 0296-24-3630
FAX番号 : 0296-25-1588
----------------------------------------------------------------------